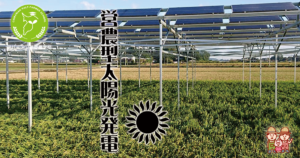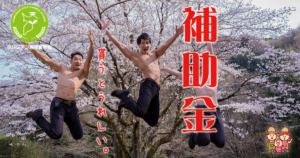営農型太陽光の今後

営農型太陽光の現状

固定買取制度が、なんとか続いているとはいえ、現状1kWhあたり10円。しかも営農型太陽光限定となっている、今後も金額が落ちていくとしたらいくらになるだろうか?おおよそ、固定買取制度の場合、9円~10円が限界と思う。しかしこの価格だとほぼ市場価格と近いところになるため、そのまま売ったらどうだろうかということもあるのだが、やはり20年間固定金額で買い取ってもらえるメリットは大きい。
さて、千葉県においては、低圧の太陽光発電所では、年間105,000kWhが平均発電量くらいだが、ここから計算すると、10円の場合、115万円(税込)となり、9円103万と続く。大体、この10倍の金額を発電施設の費用と考えるとよいため、1150万が施設費用と見なされる。現状では、10円なので1150万円で作れれば一般的な今まで販売されてきた価格となるのではないだろうか?
日本は、2050年に向けてカーボンニュートラル(炭素排出0)を目指している訳だが、この期日は世界的情勢からどんどん前倒しされることとなることが予測される。その際に、日本の狭い国土では、既にメガソーラー用地はなし、風力は時間がかかる、そんな際に災害に強い営農型太陽光の需要は増してくることが予測される。つまりどんどん営農型太陽光はやって欲しいわけだが、太陽光施設下の農業者が足りない。またFITによる買取の金額の旨味が少なくなってきている現実です。
営農型太陽光の今後

今後考えられるのは、固定買取制度の下限金額(大体10円か?)、もしくは施設建設に対する補助金、税の減免などが考えられるのではないかと推測する。そうしないと今後爆発的に増えていくことは、現状では考えづらい。ただ兼業農家的立場からいうと収益の二重化がはかれるため、やはり営農型太陽光発電はよいと思うねd[×´з`]b
高齢者年金代替に最適

「ほんとうの定年後」という統計に基づいた新書を読み込んでいるが、老後実際に必要な金額は、月に10万円だという。営農型太陽光の場合、10年間は、投資額の支払となるが、丁度11年目から20年、そして21年目から30年程度で年間100万円程度の売電を見込むことができる。後者の方は、固定買い取り制度後の取引だが、一般的に10円程度は確実に見込めるだろう。
この結果、収入として約10万円が収入として入ってくることとなり、老後生活の安定に大きな役割を果たすこととなるだろう。太陽光パネルの下で栽培などを行うならば、更に収入も増えることとなる。このような理由から、毎年の売上こそ少ないが長期間を見込んだ時には、大きな収入を継続的に運んでくれる営農型太陽光は、農業者にとって優良な投資と思える。