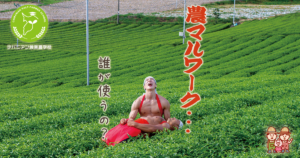営農型太陽光(ソーラーシェアリング)の現在を解説
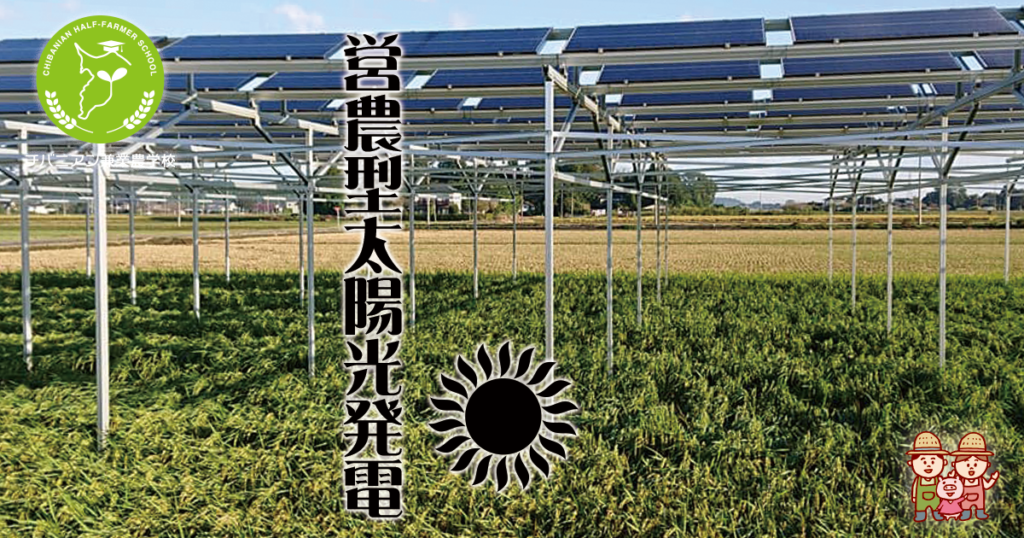
営農型太陽光発電とは
元々、これが専門なのに、一切触れずにきましたので、改めて加筆してみます。それだけ農業で他に儲かる手段があるということかもしれません。営農型太陽光発電がどれだけ農家が儲かるかを解説します。2012年くらいから、当時、営農型太陽光を唯一エクスポで講義したくらい、結構付き合い長いです。だから法制度から認可までわかっているし、会社でもやっています。
そこで営農型太陽光発電の何がポイントかというと、基本的にほぼ作業なく、不労収入が定期的に入るということだよね。それをいったら身もふたもないので誰もいわんけれど、対外的にはSDGsとか、脱原発とかいっていると恰好いいですd[×´з`]b
全量固定買い取り制度とは?
ここでは、さらにFIT(電力固定買取制度)に関して、述べると元々1kWhあたり40円で買取することからはじまり、現在は10円(2023年度)まで買取価格が落ちてきています。具体的には、大体100kWh出力の発電所で、年間10.5万kWhを発電するのが目安なので10円×10.5万kWh×消費税で、年間115万ほどの収益となります。設備費を1100万くらいで作るのが相場で、政策金融公庫の金利1.5%くらいで15年支払うと年間100万くらいの支払で、手元に40万くらい残るという訳です。(保険7万強、固定資産税も必要)利益を出さずに早く融資を返却すると10年程度で終了します。
実は、初年度個人事業主として課税事業者になると100万還付されるため、3年は非課税事業者になれないけれど、この場合年の支払いを74万まで下げられるので、40万近くは残るという計算になります。
さて、この営農型太陽光発電の要は、太陽光発電施設の下で農作業をする必要があるということです。これは当然農業者でないとならないです。そのため、現状ではなかなか農業者以外はやりづらくなっています(区分地上権をつけて、分離するやり方はあるが)
いまや農業者だけができる投資手法
しかしこの程度の金額だとうまみがなさそうと見えるが、実は返済が終わった16年目から115万でがまるまる入ってくる訳です。さらには、21年後も大体kWh10円程度での販売は可能とされているので、115万くらいの収入は見込めるでしょう。多分、それで30年目までいけるだろう。その際にパネル自体を高性能で安いものにリプレイスすることもできます。
結果的には、銀行から借りて自分のお金を使った訳ではないので、若い人であればあるほどその後長く得をする仕組みです。これは農地という初期投資時点で格安に買うことができる農業者にとっては大きなメリットだと思いますし、兼業農家は、本業の収入を与信してくれるので、さらに借りやすいということがいえるでしょう。
ただ高い買い物なので、やはりいろいろな角度からネットでもよいので調べて自信をもって購入してください。大体、一番の問題は、太陽光施設の問題ではなく、業者や施工の問題だったりします。つまり収益化の仕組み自体の問題は、ほぼありません。将来的にフリー電気ができたとか、大きな電力事情のブレイクスルーが起きた場合は問題ですが、それ以外では安心して投資できると思われます。
更なる利回りの増加
最近、ウクライナ戦争により、電気代が急速に値上がりを続け、現在は、企業と取引をすると1kWhあたり14円で買い取るまでになっているらしいです。この金額で購入してもらえれば、147万円まで売りあがるため、条件としてはよいのだけれど、この状況が20年間続くかということが懸念事項です。ただ長期トレンドでは、高値傾向は間違えないでしょう。