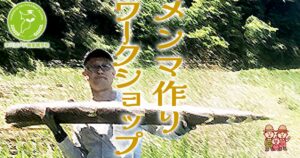首都直下型地震の確率30年内70~80%と農業

首都直下型地震は本当に来るのか?

最近、ウクライナの問題も心配ですが、世界的な出来事が直接日々の生活に関わっていることに驚きます。食料や燃料の価格が世界的に値上がりし、デフレ下日本人の生活不安をあおっていますね。
このような状況下、南海トラフや首都直下型地震の確率が30年内に70%~80%、しかも過去最大の地震になることが内閣府に予告されています。ただいつもの食料自給率向上させよう問題と同じで、具体的に自立した個々の災害対策まで政策的に落とし込めていないことが問題でしょう。
例えば1週間分、水・食糧を備蓄するというのは一時的な災害対策であって、その後に起こる災害失業や住まいの確保、慢性的な食糧・物不足などは考慮されておらず、そもそも家が潰れたら備蓄の意味もありません。
このような中で食料危機をダーチャ(畑付き小屋)によって、ソビエト末期に乗り切った農的仕組みは災害対策にもなっていくと考えています。つまり食料を自給できる、いざという時の住居を確保できるという点がとても大きいのです。つまり通常時は、宿泊付き体験農園として利用し、災害時には自前の避難所として利用し、太陽光パネルなどで最低限のエネルギーも自給できれば、長期間滞在ができる。また農園を利用する時点で地域との関係性も作れるということも大きいでしょう。
現在、50名以上の首都圏在住民が睦沢町に農地を借りる算段となったのですが、その立場になれば、いざという時の自給自足体制も作れると思います。その点では、生徒たちが進めている「農地キャンプ」の意義は災害時に発揮されると思います。地震の確率に関しては、「YOUTUBE中田大学」を見てください。関東大震災は、おおよそ110年の周期で繰り返されており、既に前回から100年経っていると聞くと厳しい状況がわかるのではないでしょうか?
稲作は、実は1反あたり年間23時間で作れる

昨年、睦沢町稲作チームの収穫が終わりましたが、初年度はさすがに、初体験の人ばかりで、本当に苦労していました。どの程度の面積をやっているかによるのですが、一人で約1トンの収穫をした人もいます。これは、20人分の一年間の消費量なので、これだけ収穫すれば、確実に家族4人くらいは自給自足ができますね。
ちなみに農水省は、稲作の作業量を機械化、大規模化が前提ですが、年間23時間ほどと見積もっています。これは全て含めてということですから、どれほど省力化されているかがわかってもらえると思いますね。この程度であれば、いろいろと工夫をすれば、兼業でも稲作ができることがわかると思います。もともと稲作は、兼業農家がもっとも多い品目であったことからも時間的優等生作物ということができるでしょう。