農地法、わかりやすく解説

農地法の目的

農地を限られた貴重な資源と位置付け、転用を規制しつつ、これまでの耕作者自らが所有する制度とともに、地域と調和した効率的利用を行う耕作者の農業上の利用を増進することにより食料の安定供給に資することを目的としている。
農地法では、農地が食料の安定供給のために、それぞれの所有者の権利を認めつつも、農地が農地以外の用途に変更することを制限する法律です。つまり農地が無秩序に他用途に転用され続ければ、食料の安定供給が危ぶまれてしまうため、この法律により、制限しているということです。
また農地法では、新規就農に関する条件を定めており、ここで定められた条件が新規参入の障壁となっています?そのため農地法を正しく理解することが就農を理解することとなります??
農地法の定義、農地、採草放牧地
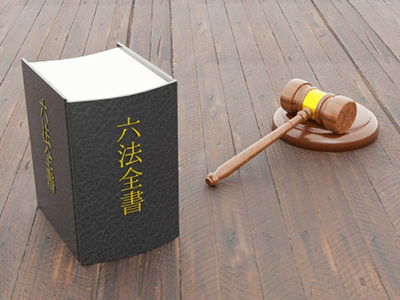
農地法において定義されるものとして「農地」と「採草放牧地」があります。ここでは採草放牧地はあまり一般的でないので無視してもよいでしょう。農地の地目として「田」と「畑」があります。
- 「農地」とは、耕作(土地に労費を加え、肥培管理を行って作物を栽培すること)の目的に供される土地をいう。
- 「採草放牧地」とは、採草又は家畜の放牧の目的に供される土地をいう。
ただし、田んぼで稲作以外を行ったり、畑で稲作を行うことも可能ですので、栽培で地目にこだわる必要はありません。
農地法3条による権利移動

農地法では、耕作目的での権利移動を3条で規定しており、この場合の権利移動は、農地→農地となり、所有権、賃借権も同様に耕作者間となります。またこの所有権等の移転に関しては、当該行政の農業委員会の許可が必要となります。
この際に農業委員会より許可を得るためには、下記の許可要件を満たす必要があります。2023年4月に最低下限面積が撤廃されたため、一番困難であった要件が無くなりました。
- 1.全部耕作要件
- 取得後に農地等のすべてを効率的に利用して耕作等を行うこと
- 2.常時従事要件(農地所有適格法人を除く)
- 原則として年間150日以上の農作業に従事すること
- 3.地域調和要件
- 周辺の農地等の効率的・総合的利用に支障がないこと。
法人の農地取得に関しては、別途要件を求められますが、複雑となるので、ここでは省略しています。
賃貸借の解約等の制限

賃貸借は、更新をしない旨の通知をしなければ、自動的に同条件で更新されることとなり、契約満了日の6カ月前までに通知を行う必要があります。もともと、この賃貸借に含めて物納及び使用貸借があり、物納は収穫物などで支払い、使用貸借は無償で貸すことなります。農地は、多目的での利用を制限されていますので、結果的に格安の貸借料となる傾向にあります。
農地の転用規制(4条、5条)

農地転用とは、農地を農地以外(雑種地、宅地等)に変更することを指します。農地は原則、農地法に守られているため、転用には厳しい基準を設けられていますが、反面固定資産税は格安に抑えられています。基本的に農地法では、優良な農地を守るというのが目的ですが、一部条件を満たし、やむを得ない場合には、農地転用を許可しています。
4条と5条の違いは、4条は農地の所有者、借権者が転用する場合、5条はそれ以外の他者が所有権や賃借権などを設定し、転用する場合となります。つまり田舎の農地などでよく見る太陽光施設などを元々の所有者が行う場合には、4条、その他の人が権利や賃借を結んで行う場合には5条ということになります。
農地法まとめ

農地法において、就農に関する部分としては農地売買や賃貸借で原則3条が関係してくることとなります。下限面積はなくなったのですが、新規就農の場合に求められる要件としては、営農日数の150日、3条に記載はないですが、技術要件などです。また古い考えの農業委員会においては、専業を重要視する傾向もあり、これらが新規参入を阻む要因となっています。
また農業者人口の急激な拡大により、使いきれない耕作放棄地があふれ、新規就農者に対して、担い手として期待される機会も今後増えてきます。その際に、全てが有効活用できる農地とは限りませんので、収入が少ない農業者にとり、なんらかの方法で農地転用や粗放栽培、農地除外による山林化なども必要となってくるものとみられます。そのため、農地法自体をしっかりと理解し、状況に応じて、様々な活用方法を新規就農者は考えておく必要があると考えられます。





