農地購入、農地転用、裏ワザや抜け道をわかりやすく解説

目次
農地法第三条、わかりやすく解説
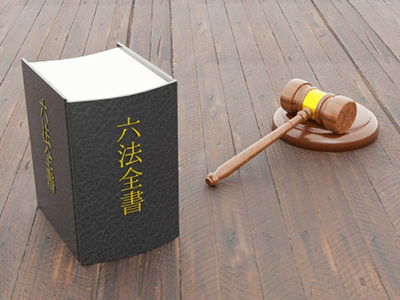
農地法第3条が規定する農地の権利の移動については、実際に農業を営む者同士の取引に限定されており、農地転用を前提とした取引を排除しています。これは、農地を農業以外の目的で使用することを防ぎ、農業用地としての利用を保護するための措置です。具体的には、農地を売買または賃貸する際には、各市町村の農業委員会からの許可が必要となります。この許可を得ることができれば、正式に農業者としての地位を得ることができるわけです。
しかしながら、この許可が下りにくい実情が兼業就農を難しくしています。農業委員会は、農地の適切な利用と農業の振興を目的としており、農業経験の少ない兼業農家や農業への本格的な取り組みが見込めない者への許可は慎重になりがちです。特に、農地を守り、農業を維持発展させようとする地域では、農業経験や農地を活用した具体的な栽培計画の有無が許可の鍵を握ることが多いのです。
農水省が示す「農地の売買・貸借・相続に関する制度」には、農地法のほかに「農業経営基盤強化促進法」も存在します。この二つの法律は、農業経営の基盤を強化し、農地の適正な利用を促進することを目的としています。農地法が農地の取引に関する直接的な規制を設けているのに対し、農業経営基盤強化促進法は、農業経営の規模拡大や効率化を支援し、より強固な農業経営基盤の構築を目指しています。
兼業就農を考える際には、これらの法律による規制や支援策を理解し、地域の農業委員会との協議を通じて、農地の取得や農業経営への参入の道を探る必要があります。農地の取得に際しては、農業経験の有無、農地をどのように活用するかの具体的な計画、地域の農業振興にどう貢献できるかなど、多角的な観点からの検討が求められます。兼業農家として農業に参入するためには、これらのハードルを乗り越えるための準備と計画が不可欠です。
農地の取得要件

一定の面積を経営すること(2023年4月廃止)- 必要な農作業に常時従事すること
- 農地すべてを効率的に利用すること
- 周辺の農地利用に支障がないこと
このような要件に、さらに適正技術要件が付け加えられています。兼業就農する際に、一番気になることは、必要な農作業に常時従事するということの日数が、原則150日となってることでしょうか?この結果、週末農業だけでは104日間。祝日をプラスして120~130日とされています。この結果、本職を持つ人は、この条件をほぼ満たすことはできないということとなります。ただし、この150日は、実は8時間労働をしなさいということではないので、何時間と具体的な指定はなく、ムニャムニャとされています。いや、本当に、読んでいてわからん。一応、農業経営も含むということでマーケティングや関連事務作業も含まれています。解除条件付き契約を結んだ場合には、常時従事要件は不要となります。
最後に周辺農地との共生という観点は、例えば無農薬を実施する周辺農地の中で、農薬を散布したりするようなことや広域で栽培を行う中で、ハウスを建てて邪魔になるような状況を指します。なので普通にやっている分には問題がないと思われます。
さて実務的な就農条件をまとめてみたのですが、この通りに農業委員会が検討してくれるかというと実際には難しいでしょう。別に裏技でなくとも就農する方法はいろいろとあるのだけれど、ほぼ先駆者もなく、公開される必要もないため、今までブラックボックスの中に入ったままでした。できれば、このブラックボックスをチバニアン兼業農学校で全国的に開けていきたいと考えています。
農地購入の裏ワザや抜け道はあるのか?

農地を購入し、その後宅地や雑種地など他の用途に変更したい場合、法律の範囲内で可能な方法を紹介します。2023年4月の農地法改正により、農地取得のための下限面積が狭くなったことは、このような目的を持つ人にとって一つのチャンスを提供しています。この改正により、家庭菜園より少し広い面積であっても農業者として認められるようになり、農地を購入しやすくなりました。
農地を宅地に変更する正規の方法としては、まず農業者になることが基本です。農業者として認められれば、農家住宅を建てるために農地を宅地に変更することが比較的容易になります。また、太陽光発電は、ソーラーシェアリングの形態で農業者が農地に設備を建てることは可能です。これらはいずれも、農地の多様な活用を促進するための合法的な手段であり、裏技や抜け道というよりは、法律に基づいた適正な手続きを踏むことが求められます。
農地法の改正が農業者になるハードルを下げたことで、農業以外の目的で農地を利用したい場合でも、農業者としての立場を法的に取得することが有効な戦略となります。近隣に在住している場合は、農地購入のための要件を満たしやすくなり、農地を合法的に他の用途に転用する道が開かれます。
重要なのは、農地を他の用途に転用する際には、地域の農業委員会や関連する行政機関との協議を進め、必要な許可や手続きを正確に行うことです。これにより、農地の有効活用と地域の農業保護のバランスを保ちながら、目的に合った土地利用が可能となります。
補足:農地法3条の解説

農地法3条の内容
農地法3条は、農地の維持・保全を通じて、農業の持続的発展を促進しようとするものです。この条文は、農地を他の用途に転用することを原則として禁じ、また、農地を取得する際の条件や、取得者の資格についても詳細に規定しています。
その背景
日本は、面積に対して人口が多い国であり、都市と田園が密接に存在しています。過去数十年にわたり、都市化の進行や経済の変化に伴い、多くの農地が商業施設や住宅地に変わってきました。このような背景から、食料供給の基盤である農地が減少すると、食の安全や食料自給率が低下し、国全体の持続可能性に影響を及ぼす可能性が高まります。
具体的な例
例を挙げると、都市部の近郊に位置する農地が、商業施設や住宅の開発によって失われていく現象は、多くの地域で見られます。この結果、その地域で生産されていた新鮮な野菜や果物の供給が減少し、代わりに遠方からの輸送が必要となるケースが増加しています。これは環境負荷の増加や、地域経済への悪影響など、さまざまな問題を引き起こす可能性があります。
農地法3条の重要性
このような背景から、農地法3条は、農地の無計画な転用を防ぐための法的な枠組みとして存在しています。農地の持続的な保全と利用は、私たちの食生活や文化、さらには国の持続可能性と直結しています。また、地域の伝統や風景を守る意味でも、農地の適切な利用と保護が求められています。
このように、農地法3条は、食の安全や環境、地域経済、文化など、さまざまな側面から私たちの生活を支える基盤としての農地を守るための法律として、極めて重要な役割を果たしています。
チバニアン兼業農学校で学んでみませんか?

この学校では、農地に関する様々な裏ワザを学ぶことができます。例えば、農地取得の方法や法律について詳しく講義するので、初心者でも安心して農業を始めることができます。現在、チバニアン兼業農学校で農家資格を取得した生徒の数は80名を超えており、実績も豊富です。当校は、栽培だけを教えるのではなく、法的な農家資格を取得することを主眼に置いているのが特徴です。栽培に関しては、修了後も継続的に学ぶことが前提となっているため、長期的なサポートも受けて独り立ちを目指します。
またチバニアン兼業農学校には、行政書士、建築士、建築会社、水道会社、電気工事士など様々な職種の人が参加しています。これにより、様々な職種の方から協力を得ることができます。三カ月のコースが終了した後も、継続的に情報交換の場を提供しており、農地取得に関する最新情報を常にインプットできる環境が整っています。また、関連の農事組合法人も持っており、法人設立などの支援も可能です。
チバニアン兼業農学校は、農地法を専門的に講義する日本唯一の学校であり、これから農業を始めたいと考えている方にとって、非常に価値のある学びの場となっています。是非、あなたもチバニアン兼業農学校で新しい一歩を踏み出してみませんか?農業の知識を深め、実践的なスキルを身につけることで、あなたの未来に新たな可能性を広げることができるでしょう。





