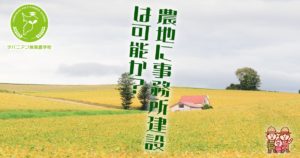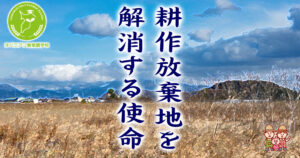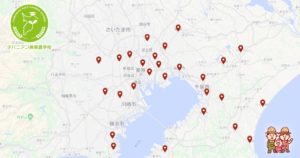法人が農地貸借を結んで農業をはじめる場合をわかりやすく解説

株式会社が農地の貸借を結んで農業をはじめることは、法律的にも許されているけれど、では何がもろもろ農地所有適格者法人と違うのかということが重要となるので、その点を農水省にも問い合わせてまとめてみたヨd[×´з`]b
所有の問題はどこにあるのか?

さて毎回問題となっているのは、株式会社に農地所有を許可した場合に、いわゆる資本の論理が入って、農地が適切に利用されないのではないかという懸念があるので、法的には厳しい縛りがある。一方で農地所有適格者法人とは何かというと農地を所有できる法人なのだけれど、こちらは売り上げの過半を農業に限るため、制限が厳しくなるのだ。つまり他にいろいろ農業外サービスの会社は農地所有法人になれないということ。
その会社などが認定新規就農者になれるのか?

また今回、僕が問題としたのは別に所有が目的ではないので、そこはよいとして(農地は借りても安いので)、通常法人(農地非所有会社)が認定農業者、もしくは認定新規就農者になれるかということを聞いて見たヨ|ェ・]y-~
懸念したのは、認定を受けるために、例えば売り上げの過半が農業売り上げが必要なのか?もしくは、その他条件がないかということです。一応、結論から書くと通常法人でも各市町村の計画に基づけば、認定が受けられるということでした。
農地基本台帳に会社名があれば、従業員は農家住宅は建てられる?

本当はさらに突っ込むと、この通常法人の農業従事者は、農家住宅を建てられるかということもあるのだけれど、これは橋本さん(当校講師・元農水官僚)の見解だと各市町村に寄るのではないかということでした。この場合には、先日書いた農地基本台帳に会社名が掲載され、かつその会社の農業に必要日数を従事する農業者が、各市町村の農業委員会が確認をするので、それが承認されれば、問題はないのかと思います。
これは何が重要かというと、農地所有適格者を得るために、法人が二重で必要だと様々な事務作業が増え、面倒になってしまうからです。また認定を受けることにより、農業者向け補助金や融資を受けやすいという側面もあり、実は兼業農家を目指すという奇特な人たちには、重要な選択となるのですd[×゚д゚]ハッ!
また単純に農地所有適格者には比較的簡単になれるので自分が借りた農地を自分の会社に貸し出すことによって、安心して営農ができるのではないかと思ったりもします。
- 参考サイト
- 認定農業者制度について
- 法人が参入する場合の要件
農地賃貸をする法人の種類
株式会社・合同会社・合資会社・合名会社・NPO法人・一般社団法人・一般財団法人