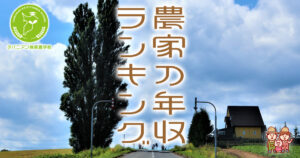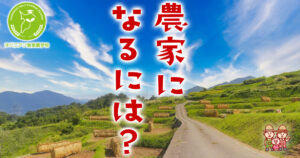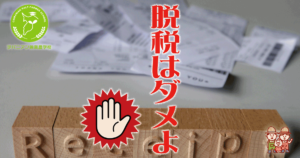農家の年収、しんどい…

農業者の平均年収

2021年における日本の農業経営体の平均所得は、農林水産省の「農業経営統計調査」によると、125万4,000円でした。この平均所得を個人経営と法人経営に分けると、個人農家の平均所得は115万2,000円、一方、農業法人の平均所得は424万5,000円となっています。農業の種類や生産する商品によって異なるものの、一般的に農業従事者の年収は150万円から300万円程度とされています。これは、一般的なサラリーマンの平均年収が約400万円前後であることと比較すると、比較的低い水準です。さらに、副業として農業を行う人々の平均収入は年間51.1万円と報告されています。農業の所得は経営内容によって大きく変わるため、会社員の収入と単純に比較するのは難しいと考えられます。
ただし、この平均所得が正しいかというと年齢や立場による考慮も必要です。もともと、農業者の平均年齢は68歳とすると、かなり高齢の人たちの所得も母数に入っていると思われます。そのため、本来ならば生産年齢である15~65歳を母数として再計算する必要があるでしょう。残念ながら年齢別の所得は見つけきれなかったため、わかりませんでした。しかしこれを考慮するとかなり状況は変わってくると思われます。
兼業農家の平均所得

平均所得は、51万円となっているようですが、中央値は約100万という調査もあるようです。兼業農家の多くは、稲作と自給農だと考えられます。もともと、一般的な兼業農家は、どちらかというと消極的農家です。また兼業農家の平均年齢は、全体の平均年齢よりさらに高い可能性があります(調査結果なし)そのため、当校生徒のような積極的な兼業農家の所得は、より高められると考えています。元の額も低いですし、取り組む意識も違います。そして収益を上げる手法が大きく違えば、この兼業農家の平均取得に関しては、ほぼ気にする必要はないといえるでしょう。
結局、農業は儲かるのか?

ただし、新規参入の専業農家の場合、かなり懐事情は厳しいと考えられます。まず年間150万の支援金などがある理由は、そもそも構造上で儲からないからでしょう。機械、施設の初期投資などがその後所得にも大きな影響を与えていると考えられます。5年後の離農率35.4%という数値が全て物語っており、これも5年後240万円しかないという現実があります。
もちろん、儲かっている農家も少なからずあります。しかし他の業界と比較して考えると、非常に率も低く、むしろ少ないからより世間で取り上げられるという構造があるように思えます。やはり平均的な農家が儲かっている状況でない限り、今後も新規参入は増えてはいかないでしょう。
兼業農家はどうなのか?

上記のような現状を踏まえ、兼業農家には独自の戦い方があるという提案を行ってきました。具体的には、新規就農者がなぜ儲からないかということを検討しなければなりません。その一番の理由としては、初期の投資額が高く、その割には栽培物の買取価格が安いため、構造的に収益率が悪い。また価格が市場に左右され、利幅が少ないのに、国際的な相場に影響されてしまっているということではないでしょうか。一方、親元就農の場合には、機械や施設をそのまま引き継げるため、収益率が高くなっています。つまり完全なる新規就農は、かなり分の悪い環境となってしまうのです。
そのような前提をもとに兼業農家を考えた場合、機械や施設がないということは、専業農家と同じなのですが、就農時点では、他に収益を求めているので、機械も施設も必要ないということがいえます。他に収益がある結果、収益化に時間がかかる果樹などの栽培物を狙うこともできます。また農村の高齢化による引退などは日常で、待てば自然と機械も施設も手に入れることができたりもします。このように最初に生活の糧を農業においていないことにより、時期を追って、必要なものを増やし、農業収益を拡充していくことができるのです。
どの形態での就農を目指すのかは、個々の人の判断とはなりますが、この中間点にあるのが、農業法人への就職ということとなるのかもしれません。どちらにせよ、世の中は自己責任ですので、何が自分にとって最も適しているかを考え、選択しないとならないのかもしれません。兼業農家として、リスクなく、収益を上げたい人はぜひチバニアン兼業農学校をご検討ください。