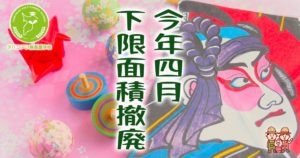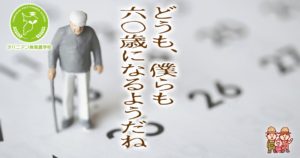食料自給率の議論はやめて、兼業就農で食料自給をはじめた方がよい。

日本の食料自給率については、国内外で様々な議論が存在します。これらの議論は、食料安全保障、経済、環境、持続可能性、農業政策など、多岐にわたるテーマに触れています。
議論のポイント
- 食料安全保障: 一部の人々は、自給率が低いという事実が日本の食料安全保障に対するリスクを示していると主張しています。国際市場の不安定性や輸入国との政治的な対立、自然災害などが供給を妨げる可能性があります。
- 経済効率: 他方、自給率を高めるためには農業への大規模な補助金や保護主義的な政策が必要となるため、これが経済効率に悪影響を及ぼすという意見もあります。リソースは他の産業や努力に使用することができ、それが経済全体の効率を高めるという主張です。
- 環境と持続可能性: 食料自給率を高めることは、地方経済を活性化させ、地域の伝統的な農業や環境を保護するという観点から、環境と持続可能性の視点で良いという意見もあります。
- 農業政策: 日本の農業政策が自給率にどのように影響を及ぼすかという議論も存在します。例えば、農業の効率性と競争力を高めるための改革、小規模な家族経営の保護と支援、若者や新規参入者を農業に引き入れるインセンティブなどが挙げられます。
これらの観点から、日本の食料自給率に関する議論は複雑であり、多くの異なる利害関係と課題が絡み合っています。最終的な解決策は、これら全ての視点を考慮に入れた上で、最も効果的で持続可能なアプローチを見つけることになるでしょう。
最近、食料自給率に関しては、議論のための議論となり、実際には就農がやりやすくなったのだから、自分で栽培するという観点をぜひ追加して欲しい。そしてそれが一番の食料の安全保障だと思う。

兼業農家で、米を作れば自給率1200%をすぐ達成できる
ウクライナの影響か、日々、生活必需品の価格が値上されていくように感じます。この大きな要因は、ウクライナでの戦争に由来するように聞きますが、農業業界では肥料とガソリン、電気代の値上が大きく経営に影響しているようです。
しかしながら兼業農家にとって、専有面積が狭いため、その影響は限定的で、こういう際には、米を代表とする食料を自給できる点は大きく、睦沢で稲作をしているグループは米が家族の自給分より、はるかに採れるのでその保存や処分をどうしようかと相談しているくらいです。
全国的な農家の数は、既に100万人を切っていると言われているのですから、首都圏在住者が親戚や知り合いに農家を持つ確率は極端に下がっている筈です。そのため、戦後すぐでは、縁故米のような親戚などから融通しあう要素がなくなり、市場を通しての購入が原則となってしまいます。
ちなみに、米は農水省の発表では、機械があれば1反(1000㎡)あたりにかかる時間は、23時間とされ、そこから約600kgがとれる計算となります。地元のJAなどとうまく連携をすることで、収益は下がりますが、兼業農家でも十分に栽培することが可能です。日本人の米消費量は年間約50kgですので、一反で約10人分の食料を作ることができるのです。実は4人家族程度であれば、カロリーで考えれば、米だけでは23時間で自給率を充足することとなるのです。