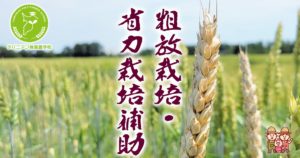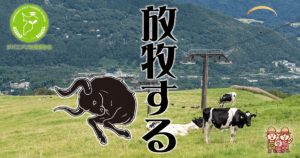耕作放棄地と荒廃農地、遊休地、その活用方法をわかりやすく解説

耕作放棄地に関して
この言葉の定義は、よくわからないという人が多いのではないでしょうか?もともと行政用語であるので、それぞれにきちんと定義があります。
さて、今回SUUMOジャーナルで「使わなくなった畑や田んぼ、どうしよう!」でその点を特集していましたので解説します。
では、用語を理解するためには、「荒廃農地」と「耕作放棄地」って同じもの?(農水省PDF)をご覧ください。
そもそもこの用語が、我々兼業就農希望者に重要なのかというと、これら耕作がなされていない農地は、割安の価格で賃貸や購入ができるからです。一般人は当然どちらもできない(貸農園をのぞく)のですが、この土地移動の権利がある点が就農者の利点です。この利点を生かしてどうするかというのを講義するのが我々の役目ですが、上記の理由もあって、悪食の人のように僕は、「耕作放棄地」「遊休地」「荒廃農地」という言葉が大好きです。なんだか夢を感じます。元田んぼとかでは、水対策が必要ですが、額縁切や明渠、暗渠などで対応が可能であり、建設用重機の免許があれば、ほとんどの田んぼなどは再生が可能だと思います。
担い手ではないが農業をしてみたい人、つまり二拠点居住、週末農業といったライフスタイルを志向する人が増えている今、荒廃農地をそうした層が利用するというニーズも出てきているようです。
「半農半Xなどニーズはあると思います。しかしそれに応えるには交通アクセスが重要。都市部とのアクセスのよい場所なら、貸しやすいし、直売場をつくって再生した農地からの収穫物を売ったりすることもしやすくなります」(小林さん)
上記のように小林さん(農林水産省 地域振興課 荒廃農地活用推進班)は、記事内で発言されていますが、まさに「チバニアン兼業農学校」の誕生を予測したかのように感じます。
…っていうか、僕の心読んだの?σ[×´∀`]σ

耕作放棄地をどう生かすのか?
耕作放棄地も二つの種類に分けられると思います。農業振興地域などで農地転用ができない場合、農地転用ができる場合です。前者の場合ですと農業者以外は購入できないため、新たな活用方法は難しいと考えられますが、逆に後者の場合ですと農業者以外でも購入が可能なため、一般的な活用が考えられます。
ただし、後者の場合でも一般的に流通しているような土地ではありませんし、一般の人が購入するためには自分で耕作放棄地を探し、地主に直接声をかける必要があるでしょう。
- 参考サイト
- 荒廃農地の発生防止・解消等

耕作放棄地の値段は?
これも農地転用ができる場合とできない場合によって価格が変わります。前者であれば、主として農地の利用しかできない訳ですから、価格は自ずと下がることになります。あくまでも私見での金額ですが、前者は100万円以上、後者は10万円~30万円程度ということになるでしょうか?これは1反(1000㎡)の購入を前提としています。
現状の分析
耕作放棄地とは、いわゆる農地の中で、一定期間以上耕作が行われていない土地を指します。簡単に言えば、使われずに放置されている農地のことです。想像してみてください。あなたが田舎の風景をドライブ中に見たとき、雑草が生い茂り、何も植えられていない土地があるでしょう。それが、耕作放棄地です。
なぜこんな放棄地が存在するのでしょうか?答えはいくつかありますが、主な理由として、農家の高齢化や後継者不足、さらには農業の経済性が挙げられます。このような状況は、田舎の風景だけでなく、日本の食料自給率や地域の生態系にも影響を与えています。
将来の見通し
耕作放棄地の問題が放置されると、さまざまな問題が生じる可能性があります。例として、土地が荒れてしまい、再び耕作を始めることが困難になることや、放棄地が増えることで地域の生態系が破壊されるリスクが考えられます。さらには、食料自給率の低下や地域の活性化の妨げとなる恐れもあります。
しかし、この問題に対して積極的に取り組むことで、将来的には様々なチャンスも生まれるでしょう。耕作放棄地を再活用する試み、例えば新しい農業技術の導入や地域住民との連携、農業体験やエコツーリズムの場としての利用など、多岐にわたる可能性が広がっています。
要するに、耕作放棄地は現在の日本の農業の課題の一つであり、その解決は私たちの生活や地域の未来に大きく関わってきます。この問題を深く理解し、解決策を模索することは、次世代に豊かな自然環境と安定した食料供給を残すために必要不可欠です。