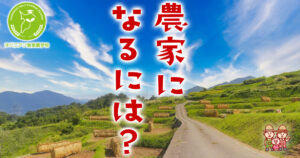一般人が農地を買うには?
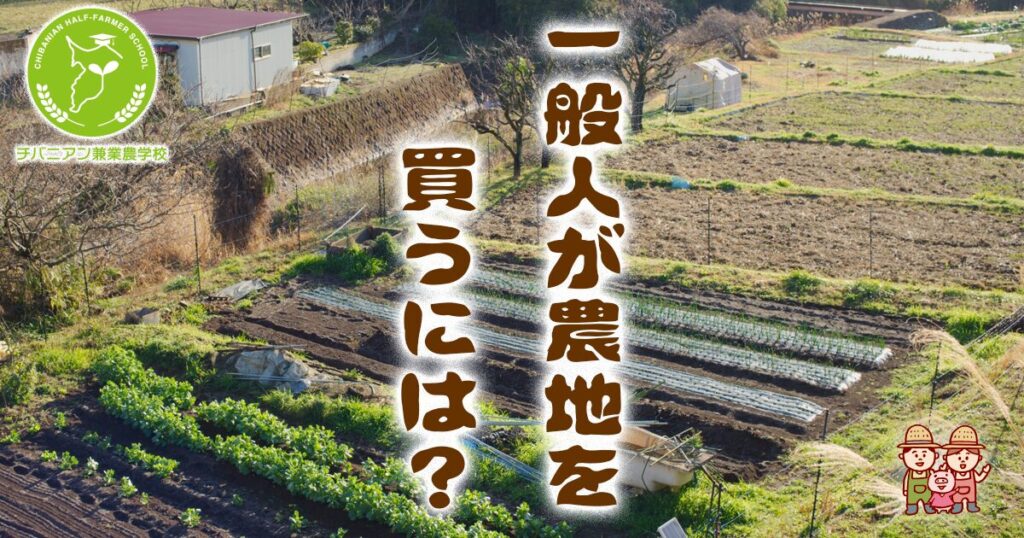
目次
一般人が農地を買うには?

なんで農地って買えないの?とても安く、広いのになんでなんだろうと思う人が多いようです。実際に農地を購入するとなると、どのような手続きが必要なのか?どんな条件を満たさなければならないのか?といった疑問にチバニアン兼業農学校で、農地取得のエキスパートとして首都圏を中心に70名近くに農地取得をさせてきた校長の平山がお答えします。もちろん、一般の人でも特定の条件を満たせば購入は可能です。
農地法第3条の基本
農地法第3条は、農地の権利移動を実際に農業を営む者に限定することを規定しています。この法律は、農地を農業以外の目的で使用することを防ぎ、農業用地としての利用を保護するために設けられたものです。つまり、農地を売買または賃貸する際には、各市町村の農業委員会からの許可が必要となり、この許可を得ることで、正式に農業者としての地位を得ることができます。その際には農地購入が可能となります。
許可が下りにくい実情
しかし、この許可を得ることは簡単ではありません。農業委員会は、農地の適切な利用と農業の振興を目的としており、農業経験の少ない兼業農家や、農業への本格的な取り組みが見込めない者への許可は慎重になりがちです。農地を守り、農業を維持発展させようとする地域では、農業経験や農地を活用した具体的な計画の有無が許可の鍵を握ります。ただし、この場合は、農地を農地のままで購入するということを前提としていますので、もし農地転用して他の用途で取得する場合には事情が変わってきます。
農地の取得要件

農地を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。
農地すべてを効率的に利用すること
農地は有限な資源です。そのため、購入した農地を最大限に活用し、生産性を高めることが求められます。
必要な農作業に常時従事すること
原則として、年間150日以上の農作業に従事することが求められます。ただし、この150日という数字は、一日8時間の労働を意味するわけではなく、農業経営に関わる様々な活動が含まれます。
周辺の農地利用に支障がないこと
自分の農地経営が周辺の農地利用に悪影響を及ぼさないようにすることも重要です。例えば、無農薬農業を行っている地域で農薬を使用することは避けるべきです。
栽培物に対する技術を持つこと
栽培しようとする作物に対する農技術を持つ必要があります。一般的には、この要件を満たすためには農業系学校や農家で研修する必要があります。
一般人でも手順を踏めば農地取得は可能

農地を購入し、その後宅地や雑種地など他の用途に変更したい場合、法律の範囲内で可能な方法があります。2023年4月の農地法改正により、農地取得のための下限面積が狭くなりました。これにより、家庭菜園より少し広い面積でも農業者として認められるようになり、農地を購入しやすくなっています。
農地を宅地に変更する正規の方法としては、まず農業者になることが基本です。農業者として認められれば、農家住宅を建てるために農地を宅地に変更することが比較的容易になります。また、太陽光発電など、農地の多様な活用を促進する合法的な手段もあります。
一般人の人が農地を購入し、農業に参入するには、農業委員会の許可が必要であり、そのためには農業経験や具体的な計画が求められます。しかし、法律の改正により、農地取得のハードルが下がりつつあり、農地を有効活用し、地域の農業保護のバランスを保ちながら、目的に合った土地利用を目指すことが可能になっています。農地購入を考えている方は、これらのポイントを踏まえ、計画的に進めていくことが大切です。
チバニアン兼業農学校では、ほとんどがサラリーマンのまま兼業農家として首都圏で就農をしています。一般人のまま、農地を取得して農家になりたい方はぜひお気軽にご相談ください。