限界集落の経営学
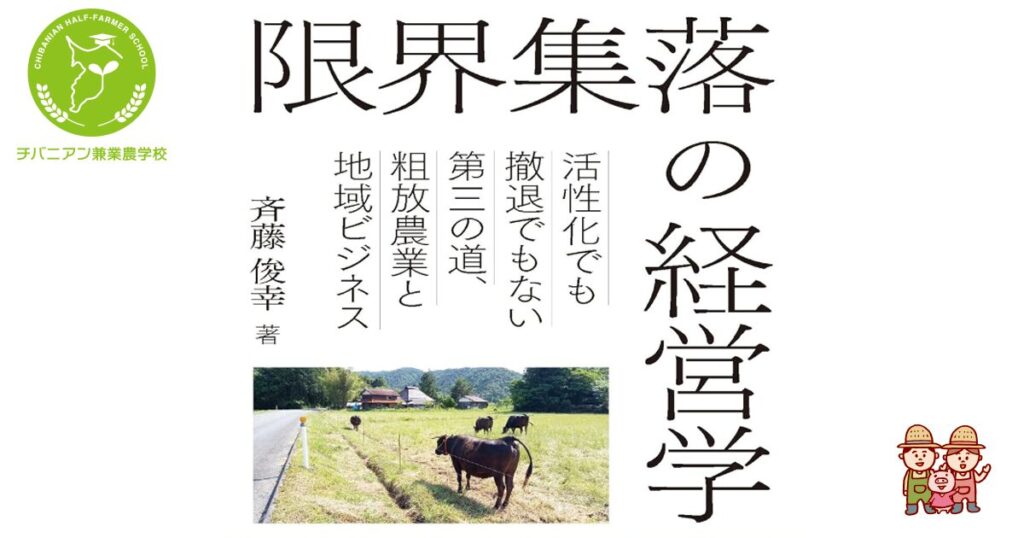
限界集落の経営学の感想

少子高齢化の波は、これからの日本の大きな影響を与えることは間違えないのだけれど、その中でも農業者の減少スピードは突出しています。それゆえ、耕作放棄地が増え続けているのだけれど、それを解決し、「むらつなぎ」を行うためには、粗放栽培による解決しかないというのが本書の大きな主張です。
もともと、限界集落とは、高齢者の人口が過半数を超え、集落自体が成り立たないようになるという定義です。さらに収益が地元に落ちなくなることも大きな問題です。筆者は、粗放栽培による収益化により、様々な事業の成功例をあげ、集落を守ることは決して不可能ではない旨を論じています。
当校も粗放栽培自体が兼業農家にとって向いているという理由で、本書同様に研究を続けています。この本の中でも取り上げられている山口型放牧は、その一例で、現在山口県庁に連絡をとり、視察場所をご紹介頂きましたので、来月には行ってくる予定です。いかに農地をうまく活用し、そこから収益を上げることができるかということを今後も研究していきたいと考えています。
しかし2400円という価格は、少し高すぎるかと思うのですが、こういう学術書に近い本は仕方ないものなのかもしれません。大学時代の教科書を思い出しましたね。
広がる廃村危機
どんなに人口が減っても農地・集落を維持する方策
広がる廃村危機。活性化か撤退かの二択では国土も食料も維持できない。住民主体の手づくり重視から、PPPによる経営力導入と中規模の加工工場への国の直接投資へ。人口が極限まで縮小しても小さな予算で農地と農村を維持する道は開ける。肉牛の放牧、受精卵、大豆ミート事業など先進事例もすである。今こそ決断の時だ。
目次
序章 限界集落の経営学
(1)地域とビジネスのイノベーション
(2)イノベーションを誘発する
(3)現場・現実から現物を差し出す
第1部 粗放農業によるむらつなぎ
第1章 活性化でも撤退でもない第三の道
1.粗放農業の延長線上に集落が荒廃しない道筋がある
2.放牧をやりたい若者は必ずいる
第2章 適正規模の農業を目指す若者たち
1.適正規模の農業とは何か
2.適正規模の牧場経営の旗を振る先駆者
3.粗放農業と相性が良い新規参入者の非競争性
第2部 新規参入者の受け入れと土地利用型地域ビジネス
第3章 後継者は長老組織からの存在承認を得る必要がある
1.「池田暮らしの七か条」が示唆する地域の思い
2.固い結束に基づく集落組織からはイノベーションは起きない
3.棚田の草刈りで存在承認を得る
4.若者が黙々と働く姿に長老組織が大規模投資を決断
5.むらつなぎ実現のための条件
第4章 イノベーションを決断できるリーダーの育成は難しい
1.多くの集落で地域ビジネスのリーダーと後継者がいない
2.組織が生き残るためにイノベーションがどれだけ重要か
3.衰退と発展の分かれ目にある浜中町農業協同組合
4.イノベーションを理念として引き継ぐ木次乳業の新リーダー
5.イノベーションを起こす当事者がいないと事業の継続は難しい
第5章 地域ビジネスを継承できるリーダーは外にいる
1.「投資と経営の分離」と「経営とオペレーションの分離」がポイントだ
2.経営リーダーは外部人材でも良いのではないか
3.弱いつながりの組織をつくれ
第6章 土地利用型地域ビジネスの実践・計画例
1.土地利用型地域ビジネスとは
2.土佐あかうし牧場クラスター ─ 適正規模農家の誘致
3.受精卵ビジネス ─ 遠隔地からのリーダーの招聘
4.子牛放牧ビジネス ─ 地域商社と牧草栽培農家の連携
5.和牛肉輸出ビジネス ─ 海外に向けたオペレーション
6.大豆ミートビジネス ─ ベンチャー企業の誘致
7.米焼酎ビジネス ─ 酒造専門家を招聘
8.農家独自流通ビジネス
第3部 国の直接投資と公民連携による所得向上
第7章 農村における公民連携
1.民間が主導せざるを得なかったまちづくりの経験
2.農家に投資を決めた大企業
3.資金調達の課題
4.土地利用型地域ビジネスによる所得向上
第8章 国の投資と地域ビジネスによる農地・農村維持
1.内発的発展論の今日的解釈を試みる
2.国も適切なリスクを負い所得倍増を果たす仕組み
3.毎年数十億~百億円の予算枠でむらつなぎは実現できる
4.むらつなぎ実現のための方策
あとがき






